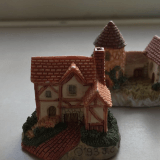おばあちゃんのところに今度、認定調査があるんだって。
どんなことをするの?
おばあちゃんは入院中なんだけど、どうなるの?



認定調査は要介護度を決める大切な調査なんだ。
でも初めてだと色々と問題があったりします。
具体的にはあとでお話しするけど、今日は認定調査でどんなことをするかを説明するよ。
入院中でも認定調査は行われるんだよ。その場合は病院で行われます。
もくじ🔖
1:【認定調査】介護保険、認定調査のシュミレーションと入院中の対応
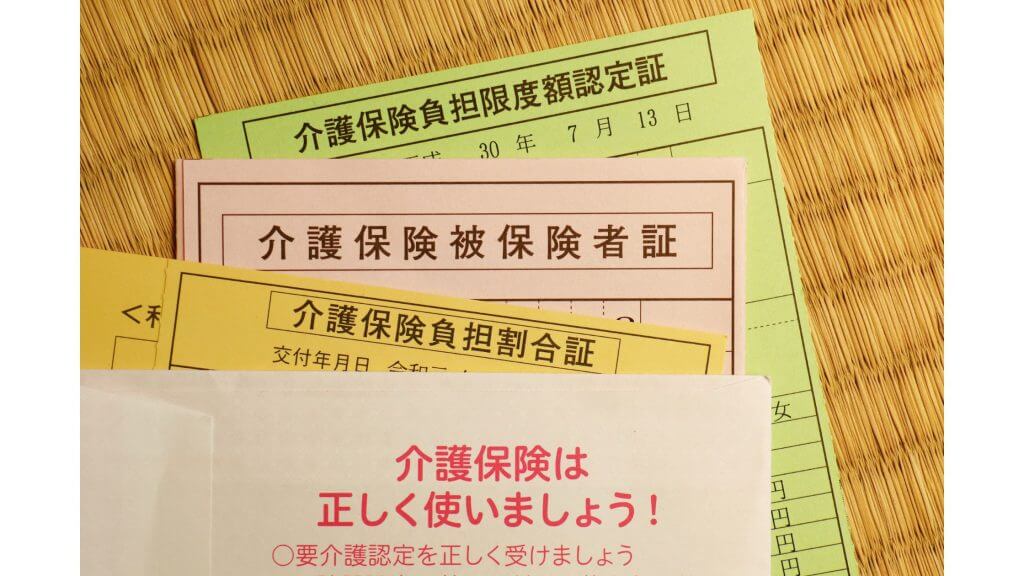
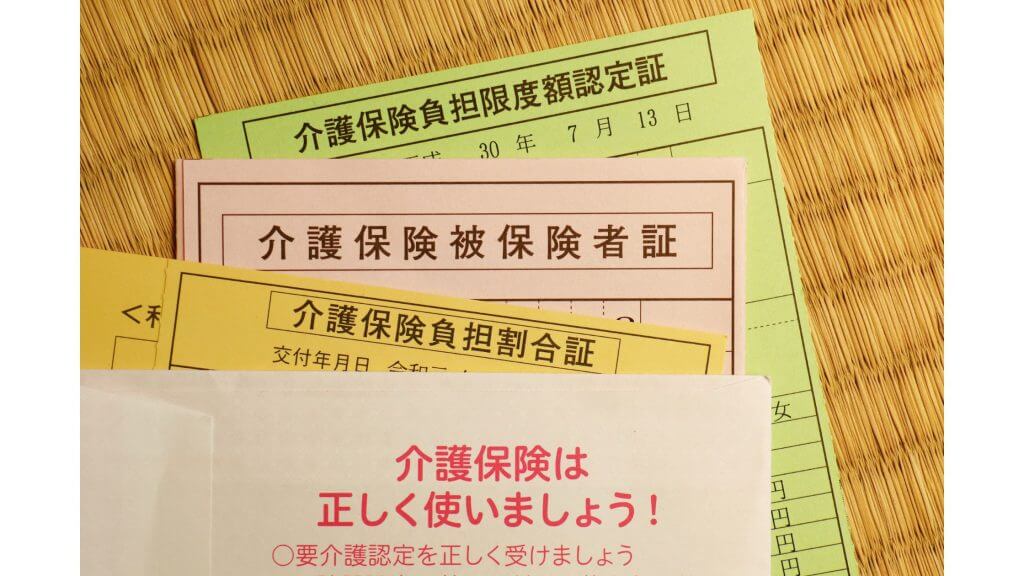
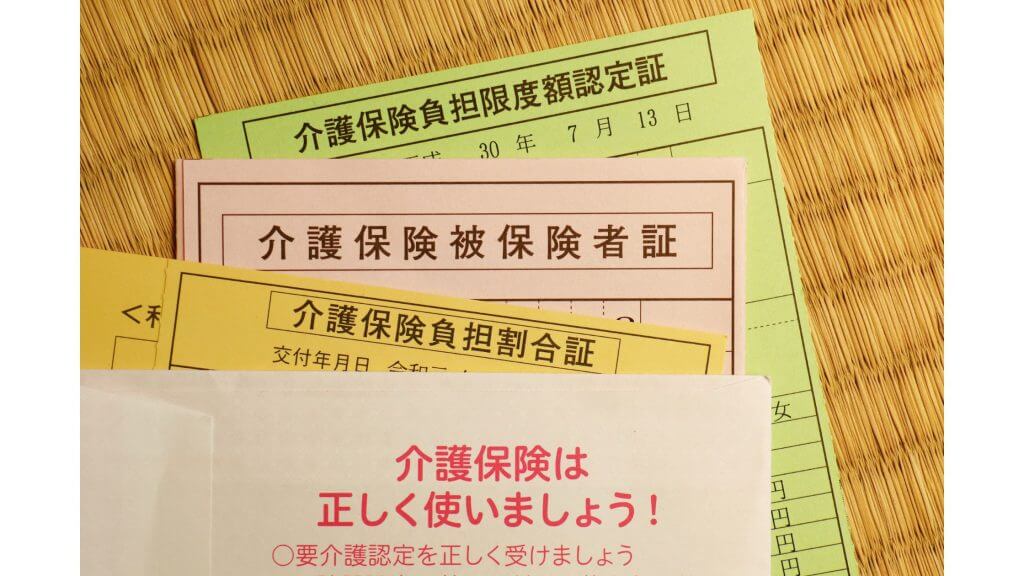
すでに要介護認定の申請はしましたか?
今日のお話は、役所に要介護認定の申請をしたあとのお話です!
役所の窓口で介護保険の要介護認定の申請が終わったら、数日後に役所の担当者から連絡が来ます。
これは「認定調査」と呼ばれる調査のため訪問の約束を取るためです。
要介護認定をする上で、認定調査は必ず行われます。
では実際に認定調査はどのようなことをするのか?
今日は認定調査の内容と、認定調査を受ける時の注意点についてお話ししようと思います。
2:入院中の認定調査。できれば入院中に認定調査をしてもらうメリットとデメリット



入院中でも認定調査は受けられます。
その場合は認定調査員に入院している病院まで来てもらいます。
私の経験から、できれば入院中に認定調査に来てもらう方が良いです。
以下に入院中に認定調査を受けるメリットをあげます!
医療スタッフが周りにいる病院では以下のようなメリットがあります。
①介護度が適切に評価されやすい。特に入院中の認定調査では「非該当」や「自立」の判定が出にくいのが大きなメリットです!
②必要に応じて病院の看護師やメディカル・ソーシャルワーカーから適切な身体能力などの情報を得られやすい(事前に病院側に、認定調査があること伝えておく配慮は必要)
③退院後の必要な介護サービスが見えてくる
④退院までに必要な検査を受ることができる
⑤どうしても家族の都合がつかず立ち会えない場合でも認定調査を受けられる(後述しますが、基本は家族の立ち会いが必要です)
ざっと以上のようなメリットがあります。
デメリットについては、、
う〜ん、あまり無いように思いますが、事前に病院の都合を確認しておくことは必要だと思います。
例えば「Dr.の診察と重なる」「検査と重なる」「透析と重なる」「看護師が忙しい時間帯に来られる」といった状況は避けた方がいいと思います。
そのため認定調査員から連絡があったら、いくつか候補の日時を教えてもらって病院の看護師さんかメディカル・ソーシャルワーカーさんに病院側の都合を確認します。
そしてあらためて認定調査員に連絡をする方がいいでしょう。
3:ご自宅での認定調査。ご両親の「何でも1人でできます」発言に要注意!



入院中の認定調査も、ご自宅での認定調査も、初回の認定調査は市区町村の職員の人が来られます(場合によっては、市区町村から指定市町村事務受託法人というところに委託されることもあります)。
いずれにしても初めて会う人が認定調査員となります。
ここが要注意です!
みなさんは初めて会う人に対して、どのような気持ちがありますか?
それも自宅で。
おそらく、「少しでもよく見られたい」。
「服はどれにしようか?」
「化粧は大丈夫だろうか?」
「髪が跳ねたりしていないだろうか?」
「部屋は綺麗かな?」などなど。
初対面の人には色々と気を遣うのが当然です。
そしてそれはお父さんやお母さんも同じです。
もしかしたらお父さんやお母さんには「1人でできない、って言うのは恥ずかしいな」という思いがあるかもしれません。
もちろん認定調査員はプロなのでその気持ちは十分承知していますが、自宅で「いつも以上に実力を出す」お年寄りが中にはいらっしゃいます。
認知症の初期の方に多いのですが、「困っていることはありません」「何でも1人でできます」と答えたりします。
記憶も”認知症の初期”ということであれば30分程度の認定調査ではクリアできてしまいます。
『でも本当は生活に困っているから要介護認定の申請をしたんですよね?』
優しい認定調査員だったらそのように考えてくれるかもしれません。
それでも「認定調査員の目で確認したこと」「本人の発言内容」「家族の発言内容」が調査の対象となるのでウソは調査票に書けません。
調査員の目で確認して問題がなく、本人も「問題ありません!」って言っちゃったら。
最後にご家族の「本当はこういうことで困っているんです!」という内容がなければ「自立」の判定となってしまい、介護保険が利用できなくなります。
介護保険が利用できないということは、もし何らかの介護サービスを使っていたら全額自己負担ということになります。
ですからご自宅で認定調査を受ける場合、誰が見ても明らかな要介護状態でなければ、ご家族の立ち合いとご家族の切なる訴えが判定に大きな影響を与えることを覚えておきましょう。
自宅での生活に困って老人ホームに入居している”要支援〜要介護1”相当のお年寄りでさえ、ごく稀に「自立」と判定されることがあります。
切なる訴えがなく客観的に判断した結果そのようになったのです。
万一「自立」の判定となったら当然申請日にさかのぼって介護保険を使うことができない上、もう一度申請からやり直しになるので結構負担になります。
そうならないために、特に初回の認定調査にはご家族の立ち合いを強くおすすめします。
4:認定調査のシミュレーション
では、具体的に認定調査ではどのようなことを確認するのかご紹介します。
ここは必ずしも知っておく必要はありませんが、急に尋ねられると困ってしまう不安があれば参考までにご覧ください。
しかし大切なことを最後に書きますので、最後は必ず読んでください。
ザックリと7つの項目について確認をします。
①身体機能・起居動作に関連する項目
・麻痺等の有無 ・拘縮(こうしゅく)の有無 ・寝返り ・起き上がり ・座位保持 ・両足での立位保持 ・歩行 ・立ち上がり ・片足での立位保持 ・洗身 ・つめきり ・視力 ・聴力
②生活機能に関連する項目
・移乗 ・移動 ・嚥下(えんげ) ・食事摂取 ・排尿 ・排便 ・口腔清潔 ・洗顔 ・整髪 ・上衣の着脱 ・ズボン等の着脱 ・外出頻度
③認知機能に関連する項目
・意思の伝達 ・毎日の日課を理解する ・生年月日や年齢を言う ・短期記憶 ・自分の名前を言う ・今の季節を理解する ・場所の理解 ・徘徊 ・外出して戻れない
④精神・行動障害に関連する項目
・被害的になる ・作話(さくわ)をする ・感情が不安定になる ・昼夜逆転 ・しつこく同じ話をする ・大声を出す ・介護に抵抗する ・落ち着きがない ・一人で出たがり目が離せない ・いろいろなものを集めたり、無断で持ってくる ・物や衣類を壊す ・ひどい物忘れ ・意味もなく独り言、独り笑いをする ・自分勝手に行動する ・話がまとまらず、会話にならない
⑤社会生活への適応に関連する項目
・薬の内服 ・金銭の管理 ・日常の意思決定 ・集団への不適応 ・買い物 ・簡単な調理
⑥特別な医療に関する項目
・過去14日間に受けた特別な医療
処置内容:点滴の管理、中心静脈栄養、透析、ストーマ(人工肛門)の処置、酸素療法、レスピレーター(人工呼吸器)、気管切開の処置、疼痛の看護、経管栄養
特別な対応:モニター測定(血圧、心拍、酸素飽和度等)、褥瘡の処置、カテーテル(コンドームカテーテル、留置カテーテル、ウロストーマ等)
⑦日常生活自立度に関連する項目
・障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)
・認知症高齢者の日常生活自立度
以上の項目の確認があり、この結果をもとに一次判定が行われます。
この後、二次判定があります。
二次判定はご本人やご家族に対応していただくことはありません。
介護認定審査会というところで「主治医の意見書」「概況調査」「一次判定の特記事項」を用いて二次判定が行われます。
しかし、この二次判定でご家族の発言が加味されるので、仮に一次判定で「自立」の判定であっても二次判定で「自立」の判定を覆すことができるのです。
もちろん虚偽の発言はダメですが、ご本人やご家族が本当に困っていることがきちんと伝わっていないと介護保険が使えない結果になることがあるので、本当に注意が必要です。